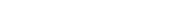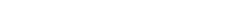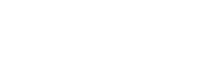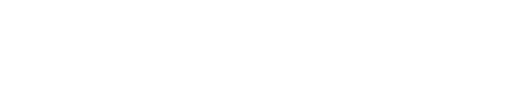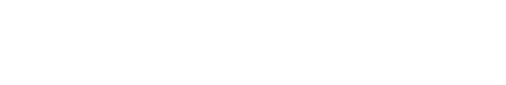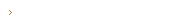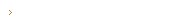≡ Menu
合格実績
幼児部合格実績
鳥取大学附属小学校 過去3年の実績
(55名合格/58名受講生)
小学部合格実績
鳥取大学附属中学校 5年間連続全員合格
青翔開智中学校 4年間連続全員合格
湯梨浜中学校
麻布中学校合格
愛光中学校合格
ラ・サール中学校合格
中学部合格実績
Beeゼミナール受験クラス全員合格!
高校部合格実績
~2025年度~
国立大学
大阪大学
工学部
合格体験記はここから
九州大学
経済学部
合格体験記はここから
神戸大学
医学部保健学科
合格体験記はここから
岡山大学
経済学部
島根大学
理工学部
島根大学
医学部看護学科
合格体験記はここから
鳥取大学
工学部
愛媛大学
工学部
山口大学
理学部
滋賀県立大学
工学部
合格体験記はここから
下関市立大学
経済学部
合格体験記はここから
北九州市立大学
経済学部2名
合格体験記はここから
私立大学
自治医科大学
同志社大学
生命科学科
同志社大学
理工学部2名
立命館大学
薬学部
立命館大学
生命科学部
立命館大学
理工学部
京都薬科大学
合格体験記はここから
大阪医科薬科大学
近畿大学
薬学部
明治大学
法学部
中央大学
法学部
関西外国語大学
英語国際学部
京都産業大学
外国語学部
武庫川女子大学
薬学部
岡山理科大
生命科学部
川崎医療福祉大学
合格体験記
2025年度
神奈川県立横浜翠嵐高等学校 合格
A.Kさん
翠嵐高校に行こうと決めたのは中1の冬くらいで、自分は将来医師になりたいので県外に出て頑張りたいと思いました。横浜翠嵐高校は、神奈川県の高校の中でもレベルが高く、もちろん勉強が重要視されるのですが、部活や文化祭、体育祭、球技大会など高校生活を楽しめる行事も充実しているため、全てを全力で頑張りたい私にとって最高の環境だと思い、受験しました。
ビーゼミでは数学の個別授業を受講していて、難しい問題をひたすら解いていました。わからないときは先生に聞くとヒントを下さったり、模範解答ではない解法を教えて下さったりしたので、問題に対して様々なアプローチができるという能力が鍛えられました。基本から応用まで幅広く練習しました。数学ではとにかく問題をたくさん解いて経験値をためていくことが大切だと学びました。
2025年度
大阪大学 工学部 合格
E.Hさん
こんにちは。僕がみんなに伝えられることは少ないですが、少しでも役に立てばいいなと思って、僕が受験を通して感じたこと、得ることができたことを記そうと思います。
まず伝えたいことは共通テストの重要性です。これは難関大学を志望している人に多く見られる傾向なのですが、入試での配点が二次試験よりも少ないため、共テに割く時間が少ない人が多くみられます。もちろん難易度が高く差がつきやすい二次の対策に時間を費やすことは悪いことではないのです。しかし、共テの得点は自分が出願する大学の指針になるとともに、入試の配点にある程度の割合(地方国立、ブロック大で5割前後、旧帝などで3割程度)を占める共テを侮ってはいけません。正直、共テが思うように取れず、出願先を第一志望から下げる人は何人もいます。そして最近の共テは科目の習熟度がもろに出ます。時間内にあの難易度の問題を解き終えるにはきちんと解き方を身につける必要があり、直前の詰込みによる付け焼刃は全く意味がありません。僕も実際共テ1週間前に教科書の内容をやっと終わらせた化学は本番5割を切ってしまいました。共テは勉強すればするだけ伸びるので二次試験対策しかしていないという人は少しでも時間を割いてみて下さい。
次に、大学受験で最も必要な能力について伝えます。それはズバリ「読解力」です。一見国語にしか使わない力かと思いますが、読解力が身についているかどうかは勝敗を大きく分けます。先述した通り、最近の共テは時間に対しての難易度が高いです。その要因は文章量の多さです。当たり前ですが、問題文に解き方は書いてありません。つまり、自分で長い問題文の中から問われていることを適切に抜き出し、解法を考えるということを限られた試験時間で何度も繰り返します。読解力が身についていない人は文章から抜き出すことが中々できず、そこに時間を使ってしまったり、見当違いのことをしたりします。読解力が弱い人はどの教科でも自分の力を出し切れず、その上根本の原因である読解力ではなくその教科の勉強に力を入れてしまうため、得点が伸びにくく、勉強時間も無駄にしてしまうことが多いです。そんな読解力を鍛える方法は文章を多く読むくらいしかないと思うので、心当たりのある人は是非意識してみて下さい。
長くなりましたがご精読ありがとうございました。
2025年度
九州大学 経済学部経済工学科 合格
D.Hさん
僕たち旧3年と違って静かに自習室で勉強できている未来ある若者に勉強のアドバイスはないと思いますが、僕が受験で役立ったことをいくつか記そうと思います。
まず、共テにおいても、2次試験においても、どういう点の取り方をするのかという作戦を早めに考えることです。作戦を練るのは当たり前と思うかもしれませんが、僕はこれを皆さんに早いうちに、なんなら今すぐやって欲しいです。なぜなら、早ければ早いほど自分が点数を稼ぐと決めた教科に時間を割くことができるし、これからたくさんある共テ演習を通して思うように点数が伸びなかったときに、点数の取り方の計画のやり直しが効くからです。
次に無駄な演習を省くことです。これは人を選ぶかもしれません。僕は数学の問題を解くとき、答えが出るまでのプロセスをとても大事にしていて、演習においては答えが違っていても答えを導く手順があっていればいいということにしていました。(大前提、計算ミスなく答えを合わせる力は絶対に必要です。)なので、答えは違うが解法はあっている問題などは間違い直しをすっ飛ばしてより多くの問題に触れられるようにしてきました。賛否はあると思いますが、面倒くさがりな僕にとってはこの方法が1番良かったと思います。
最後に力を出し切ってください。受験で一番悔しいことは、ポテンシャルがあるのにそれを出し切れないことだと思います。そんな人を何人も見ました。本番の緊張に吞まれないように、メンタルを鍛えておいてください。意外と上手くいくものです。
皆さんの成功をお祈りしています。
2025年度
神戸大学医学部保健学科検査技師専攻 合格
M.Fさん
私は元々京都大学の人間健康化学科を志望していましたが、不合格となってしまったので、後期でこの学科を受験しました。受験を振り返って、第一志望に合格するためには何が足りなかったのか、自分なりにいろいろと考えたことを話していこうと思います。
私は元々国語と英語が得意で、特に国語は共テ模試で8割を切ったことはほぼありませんでしたが、反対に、数学と理科が苦手で、冠模試ではかなりひどい点数を叩き出し、数学では2,3回0点を取るほどでした。理系科目ができないことは自分でも分かっていましたが、理系学部じゃないと自分のやりたいことができないと思い、理系を選びました。でも後からいろいろと調べてみると文理融合の学部なら、文系で入学しても理系寄りの勉強ができたとわかり、その学科でなければ!という固定観念に縛られてしまっていたなと感じます。また、苦手でもやればできるようになるだろうと楽観的に考えていましたが、意外とできるようにならず、とてもしんどかったです。大学で医学系の勉強をしたかったから理系を選んだとはいえ、何度も文系にすればよかったと思いました。絶対にその学科でないとできないことがあってそれをやりたいという気持ちがあれば自分の得意不得意に関係なく選んでほしいと思います。でも、現役で旧帝以上に受かりたいとか、この大学に入りたいという気持ちが強い場合は、自分の得意科目を活かせる入試方式を選ぶことが大切だと思います。
〇理科について
・化学重要問題演習:この本をもっと何周もすべきでした。(B問題も含め)
・化学の新演習:有機分野の問題量が他の問題集よりも圧倒的に多く、構造決定を極めるのにぴったり!
私は時間がなかったので頻出分野だけに絞ってこの本を使いました。
・生物基礎問題精講:問題量が多すぎず、全体をざっと復習するのにぴったり。
・大森徹の講義シリーズ:とにかくめちゃくちゃわかりやすい!
理科は努力と結果が直結しやすい科目なので、今になって考えると、やっぱり理科(特に化学)を3年になるまでに一周しておくべきだったなと思います。新3年生の人は今更言われても、と思うかもしれませんが(私も去年思いました。)、今ならまだ間に合うので夏までに終わらせましょう!
〇数学について
・せか京:特に図形分野がとても役に立ちました。
・青チャート:基本例題をもっと周回して、重要例題などの難しい問題も解き方を覚えるために、解けないにしてももっと解いておくべきだったかなと思います。
3年生になると急に理科の比重が重くなって数学にかけられる時間が減り、数Ⅲの演習量が数Ⅰ、数Ⅱと比べて少なくなってしまったと思います。
私は1月くらいまで京大の数学が全くできず、手も動かず、1完できたら万歳三唱という感じでした。でも、自由登校期間、塾で小林先生の個別授業を受けてそれを復習してということを繰り返していたら急にピースがはまって手が動くようになりました。衝撃でした。最終的には2完を目指せるラインまで持って行けたので(本番できるかは別として)、数学が今はとても苦手な人もどうにかなる可能性があるので、希望を捨てないでほしいです。
〇国語について
1,2年の古典の定期テストをガチって勉強していれば共テの古典は対応できます。私は定期テスト前に詰め込んだ知識に3年になってからだいぶ助けられました。3年の春からでも間に合うと思うので時間があるうちにやりましょう。現代文は逆説の接続詞や、言い換えの「すなわち」などの語の後に答えにつながる文が来るので、それに注意して読むと良いと思います。
〇英語について
英文解釈をやると良いと思います。鉄壁という英単語帳があって、私は結局買わなかったのですが、直前になってからやっぱりやっておけば良かったと思いました。難関大ほど出てくる単語が難しく、単語を知っていると、意味を推測する手間が省けるので、多くの単語を知っているに越したことはないです。京大・東大志望の人は結構使っていました。和文英訳は学校の先生に頼んで添削してもらうのをおすすめします!私は和文英訳があまり得意ではなかったのですが、問題文をとにかく簡単な日本語に言い換えるというコツを教わって、できるようになりました。
学校は進度が遅いので自分で進めましょう。また、定期テストは、定期テストのために勉強するのではなく、受験を見据えて基礎を固めるために定期テストを使うという意識で勉強すると良いと思います。3年になったらもう時間がないように感じて焦ってしましますが、時間は意外とあります。振り替えると、私は3年の前半特に焦っていて、理論化学分野で特に、一つの問題の解き方を深く理解しないまま、無理やり自分を納得させて次に進んでしまっていたなと感じます。3年の後半になってから、原理を理解した方が解き方も身につくということに気づき、そこからはYouTubeなどを活用して完璧に理解するようにしました。また、理系であれば受験が近づけば近づくほど、理科と数学にほとんどの時間を割くことになるので、そうでない科目は最初のうちにやっておくと良いと思います。
模試の判定はあてにならないとよく言われますが、どの模試でも安定してC判定以上が出ている人は受かっている印象があります。逆転合格はかなり難しいと思います。勝手に思っていることなのですが、数学は得意だけど他の科目が固まっていなくて判定が悪いような人は逆転しやすいのではないかなと思います。逆転合格を目指すなら、自分は追う側であることを理解して死ぬ気でやる必要があると思います。私は限界まで自分を追い込むことができなかったので、そこが敗因かなと思います。
まだ時間があるので焦らずに、理解を積み重ねていってほしいと思います。応援しています!
2025年度
島根大学 医学部看護学科 合格
H.Fさん
志望校は高校1年のときから決めていました。もともと養護教諭を目指していたことと、地元から離れたくない思いがあったので、できるだけ近くで養護教諭の免許が取得できる島根大学に決めました。受験を意識して勉強を始めたのは高校2年の冬頃で朝早く登校して勉強する習慣をつけるようにしました。
ビーゼミでは個別1:2の数学を高校3年の夏から受講していました。単元ごとの教科や共テ対策の教材を渡して下さったおかげで、授業だけでなく家でも数学に触れる時間が長くなり、成績も上がりました。今まで数学が苦手だった私は、問題を解きまくるだけでも十分に伸びました。数学に関してはビーゼミでいただいた教材のみで勉強しました。受験勉強に行き詰ったときは、友達とご飯を食べたり、いつもと違う場所で勉強したりと気持ちを入れ替えるようにしていました。
「絶対この大学に行く」と思っていても、何かの影響で志望大学が変わることはいくらでもあります。教科を取捨選択せず、全教科勉強していける大学の幅を増やしておくのが良いと思います。受験勉強ははやめに取り組むにこしたことはないのですが、1番大切なことは高校生活を全力で楽しむことです。
高校生活も受験も楽しんでください!
2025年度
滋賀県立大学 環境科学部環境建築デザイン学科 合格
Y.Fさん
私が本格的に受験勉強を始めたのは3年生になってからでした。もっと早くから勉強しておけばよかったと何度も思いました。特に単語は1日でも早く始めるべきです。
勉強は量も質も大切ですが、共テ対策は特に量を意識していました。どの教科に関しても、問題と時間になれるためには思っていたよりも多くの問題を解く必要がありました。特に国数英は時間配分がとても重要で、何回も時間を計って解いて練習しました。
私は本番の共通テストで目標点数に届くことができませんでした。このまま第一志望に挑戦するのか、出願大学を変更するのか、今までで一番悩みました。平均点や判定、これまでの模試を踏まえ、1番に自分が学びたいことを優先してレベルを下げて出願することにしました。目指していた大学を受けたかったという思いはもちろん残りましたが、今はこの決断をして良かったと思っているし、さらにそう思えるようにこれからの大学生活を全力で頑張りたいと思います。
出願してからはとにかく過去問をたくさん解きました。2次試験は自分1人では解決できない問題が多いので塾で先生と一緒に解いてもらうのが一番です。その時間がなかったら2次試験に対する不安を解消できていなかったと思います。
受験期は悩むことも沢山あったけれど、友達や家族、塾や学校の先生たちに相談して最後まで頑張ることができました。本当に感謝しています。自分が最終的にここだと決めた場所に合格し、そして何より受験を通して実力だけでなく自分自身も成長することができで良かったです。
2025年度
下関市立大学 経済学部国際商学科 合格
A.Fさん
僕は部活を引退したタイミングでビーゼミに入りました。ビーゼミは学校から近く、夜まであいているので自分にとって行きやすい塾でした。
僕は勉強を始めるまでは学校成績で学年の下から一番を争っていました。この状態から共テの点数を爆上げすることができたので、もし今これを読んでいるあなたの成績が学年で逆トップ状態なのであれば、是非この先も読んで欲しいと思います。
勉強面について
僕は最低限の基礎さえも皆無だったので、最初に教科書の基礎問題よりも数段簡単な問題からやり始めました。数学は入門問題精講、化学はセミナー化学、物理はリードαをとりあえず最初から最後まで全部やってから演習に入りました。地理は元から得意だったので、たまに共テの過去問を解いていました。英語に関してはとにかく単語を覚えて過去問を解きまくってください。「英語とか全く読めねーよ」とか思っている人もいると思いますが必要な単語を覚えるだけでも変わります。ターゲットの700まででもいいのでやった方がいいと思います。あとは長文を読むコツを掴んでください。コツを掴んでからはスルスルと読めるようになるので、コツを掴む機会を増やしてください。僕がコツを掴んだのは12月半ばでした。国語は点数が上下しにくい教科なので定期的に過去問を解いてゆっくり点数を上げていくのが一番だと思います。
共テについて
人それぞれ得意教科と苦手教科があると思いますが、バランスよく点を取れるように勉強した方が良いと思います。よく ”苦手教科を苦手じゃなくするより得意教科を伸ばした方が良い” 言われますが、それは直前での話です。どんなに苦手でも3か月もあれば共テで人並みぐらいに点が取れるようになります。また、得意教科だと思っていた教科が本番でコケたときに助けてくれるのは勉強してきた教科です。実際に僕も数ⅠAでコケましたが国語の点が良かったおかげで全体の点数で見るとそこそこの点数を取れました。
精神面について
前提として僕は勉強が大嫌いです。僕の他にも勉強が嫌いで受験勉強が苦痛で仕方ない人がいるかもしれません。そんな人たちに向けて僕がしていた勉強のやる気を維持する方法を紹介します。「自分は勉強が大好きで楽しい」と思い込むことです。最初の方が別に面白くもなんともないんですが、思い込んでから時間が経ってくると薄っすら面白く感じてきます。面白いと思えるようになってからは精神的にもそこまで追い込まれないし、点数の伸びもめちゃくちゃ良くなります。義務的に勉強している人が夢中になって勉強している人より伸びることは滅多にないですしね。他にも、志望校を早く決めることも大事です。成績が落ちてきて不安になることもあると思いますが、不安なときほど勉強してください。ペンが動いていると精神が安定してきます。
最後に
後悔しないように最後までやりきってください。あと大学でやりたいことが明確に決まっている人(医学部に行って医者になる、的な)以外は中期と後期はちゃんと受けた方が良いですよ。
2025年度
北九州市立大学 経済学部経済学科 合格
S.Iさん
3年の6月から勉強を始めて、まずは数学の入門問題精講をしました。数学は元々好きだったからすぐ終わり、次に基礎問題精講に取り掛かり、何周かしてから共テの過去問とかを解いていました。僕は数学の授業を受講していましたが、塾の授業では自分の解き方よりもスマートで気づけたら気持ちいい小林先生の解答を聞いて、新しい考え方として自分でも使えるように吸収していくのが良いと思います。
英語は元々1年のときからターゲットの1000までは覚えていたので1500まで覚える作業をしながら長文を読んで英語に慣れようとしました。英語は共テだと精読よりも流し読みしないと時間が間に合わないからある程度読めるようになったら速く読む練習をした方が良いです。
国語の現代文は元々8割以上を安定して取れていたから漢文の勉強をしました。古文はしようと思ったことは何回もあったけど結局共テまで勉強しなかったです。勉強しなくても雰囲気読みで45点中25点くらいは取れていたから大丈夫だと思っていたけど、本番で0点を取ったので勉強しなかったことを本当に後悔しました。
これを読んでいる後輩の皆さんへ、勉強のやる気が起きなかったとしても英単語だけは1,2年のうちに終わらせておいた方が良いと思います。3年から覚え始めようとしても時間がかかり周りに後れを取るからです。頑張ってください。
2025年度
北九州市立大学 経済学部経済学科 合格
Y.Tさん
僕は元々岡山大学志望で受験勉強を始めたのは3年の5月くらいからでした。夏休み前まではずっとE判定だったけど、夏休みの間ずっと自習室で基礎問題の演習を積んだ結果、やっとD判定やC判定を取れるようになりました。でも本番では得意な数学で点数が稼げず、岡大は諦め、志望校を変更しました。
ビーゼミの授業は数学と英語と化学基礎を取っていました。
数学は小林先生の授業に何とか食らいついて、わからなかったら終わった後にすぐに質問した方が良いです。復習は絶対にやった方が良いです。3年になったら全部忘れています。
英語はまず単語から。ターゲットは1900のうち1100くらいまでできたら勝てます。あとは文脈から予想が効きます。長文はまじで毎日読んだ方が良いです。英語新聞のアプリを朝食のときに見るのをおすすめします。
化学基礎は1か月授業を受ければ8割いけます。
因みに勉強量やメンタル面では3年が始まって共テまでが1番きついです。共テ後は勉強する科目が減るし、学校が自由登校になり、行かなくてもいいのでぶっちゃけ楽です。
2次が終わったときの解放感はまじでやばいので最後まで頑張ってください!
2025年度
京都薬科大学 薬学部薬学科 合格
R.Yさん
私は1年の間に進路の授業などを活用してどの学部に行きたいかを調べた。2年になり大学を調べたり、オープンキャンパスに行ったりして、具体的な大学まで決めた。自分の得意科目を活かせるような入試方式であること、国家試験の合格率が高く留年率の低い大学であることを基準に選んだ。
3年の夏までは数英理の記述力、応用力を中心に勉強していった。物理は公式の暗記ではなく、公式の成り立ち、意味を理解するようにしていた。そうすると初見の問題や少し形の変わっている問題へ対応することができる。化学は3年の夏までに理論を固めて、無機・有機を3年の春休みに先取りしていると暗記が楽になる。英語はターゲットを何回も何回も周回して最低1500まで、できることなら1900まですべて覚えて欲しい。例文もセットで覚えておくと英作文のときに使える。教科書に出てくる頻出単語は、入試に必須な単語であるため必ず押さえていた。
ビーゼミの数学の授業は導入がしっかりしているため予習はほとんどいらないが、授業のスピードは学校に比べて早めであるため、復習をしっかりしていると定着すると思う。英語は先生が配る構文プリントをしっかり覚えるととっても入試に役に立つ。物理は応用問題が多めであるため事前に家で基礎が固めてあると効率的に授業が受けられる。
私が受験勉強に使った参考書は、基礎問題精講(物理・化学・数学ⅠA・ⅡBC)と面白いほどわかるシリーズ(化学・物理)、センター過去問である。センターの過去問は、数学は塾でもらえるが、物理・化学はネットで調べて解いておこう。
私が受験期に不安になったときに相談したのは、塾の先生、担任、友達だ。一番友達に相談したときがリフレッシュできたと感じる。
私は基礎を中心に勉強したことで共テ直前のパック模試では78%取れていた。(参考に2年の共テ模試では35%ほどだった)しかし、本番は前日から緊張で一睡もできず、力を出すことができなかった。全然ボーダーに足りず国立薬学部を諦めざるを得なかった。落ち込んでいた時に塾の先生が、友達が励ましてくれて私立の受験のときは切り替えることができた。
共通テストは一発勝負である。その場で力を出せるかは運も関わる。力を出せなくてもそこで諦めて欲しくない。ずるずると引きずらず積極的に友達、先生、家族に相談して切り替えてください。必ず努力は裏切りません!きっとうまくいきます!